カテゴリー: ICT Concierge
-
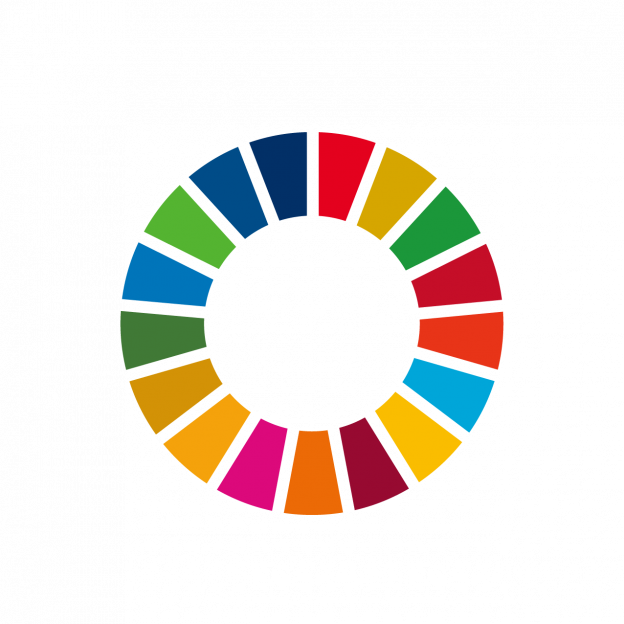
未来を明るくする商品ってどんなもの?小学校特別支援学級でSDGs-PBLを実施しました
—
by
in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 品川2026年2月13日、品川区立宮前小学校様にて、SDGs-PBL「未来を明るくする商品ってどんなもの?」の出張…
-
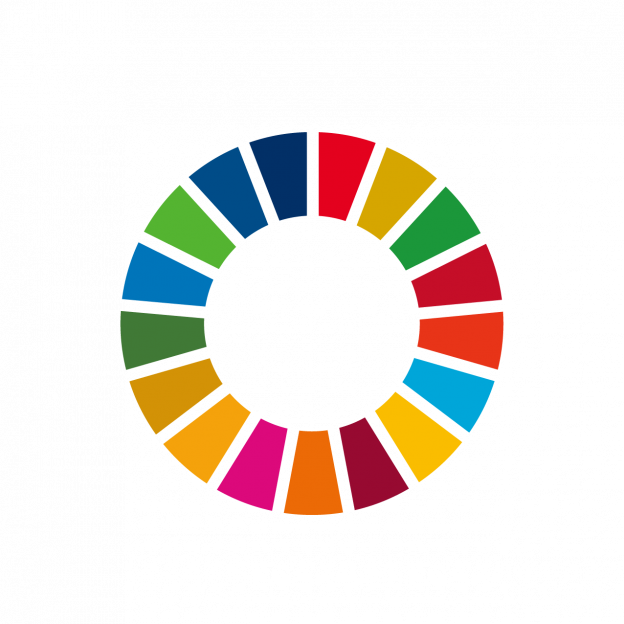
共に創ろう持続可能な社会第八弾!〜ネイチャーポジティブとデータ駆動社会の共創〜
—
by
デジタルの力で自然と社会の関係を捉え直す時代。ネイチャーポジティブとデータ活用が出会い、共創による持続可能な未…
-

-
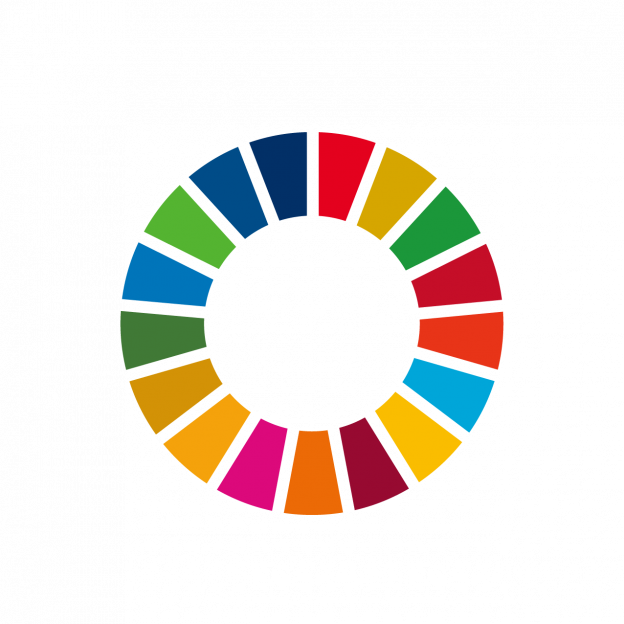
自由学園初等部でプラスチック容器包装リサイクル推進協議会の出張授業をコーディネートしました
2025年10月30日、有限会社ラウンドテーブルコムのコーディネートで、SDGsの視点を入れた「わたしたちのく…
-

-
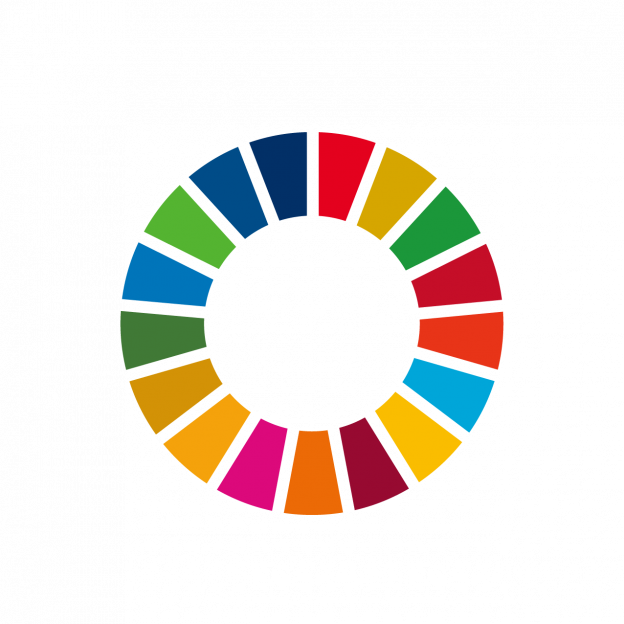
品川区立御殿山小学校でプラスチック容器包装リサイクル推進協議会の出張授業をコーディネートしました
2025年10月8日、有限会社ラウンドテーブルコムのコーディネートで、SDGsの視点を入れた「わたしたちのくら…
-
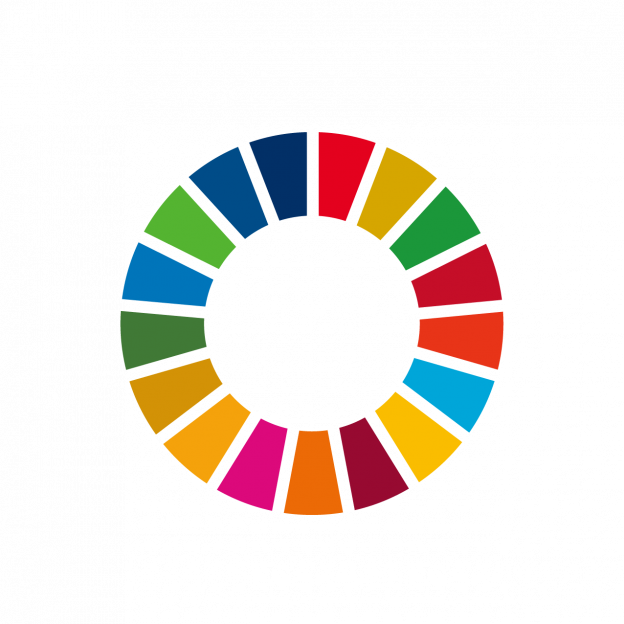
品川区立日野学園でプラスチック容器包装リサイクル推進協議会の出張授業をコーディネート(2年目)
2025年9月19日、有限会社ラウンドテーブルコムのコーディネートで、SDGsの視点を入れた「わたしたちのくら…
-

-
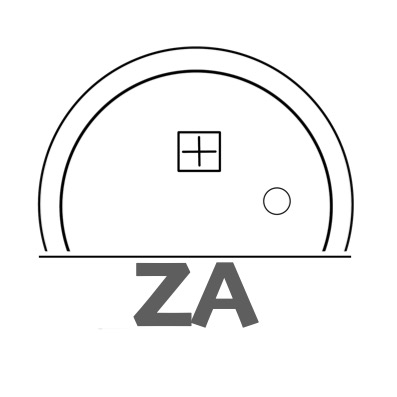
デジタルきっず育成と「まちおこし」第1回 ZAサミット
—
by
in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, Rubric, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 品川, 愛媛, 湯沢2024年度 第1回 ZAサミットをリアル+オンライン開催します。 日時:2025年3月30日(日)午前10時…
-

-
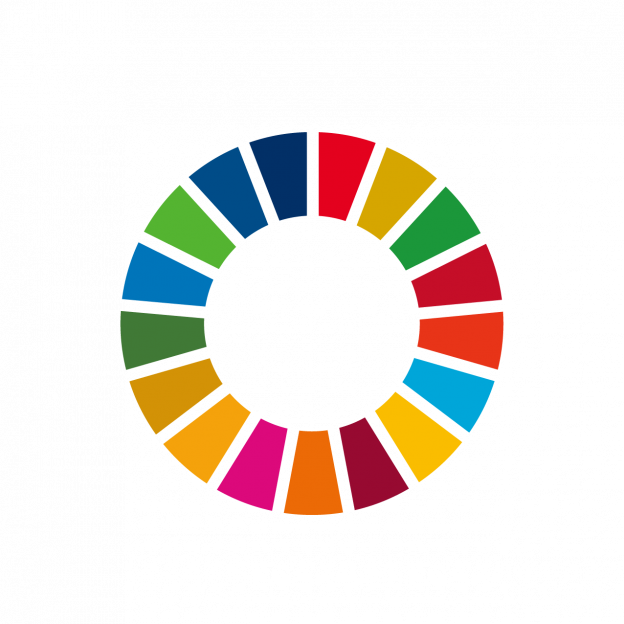
-
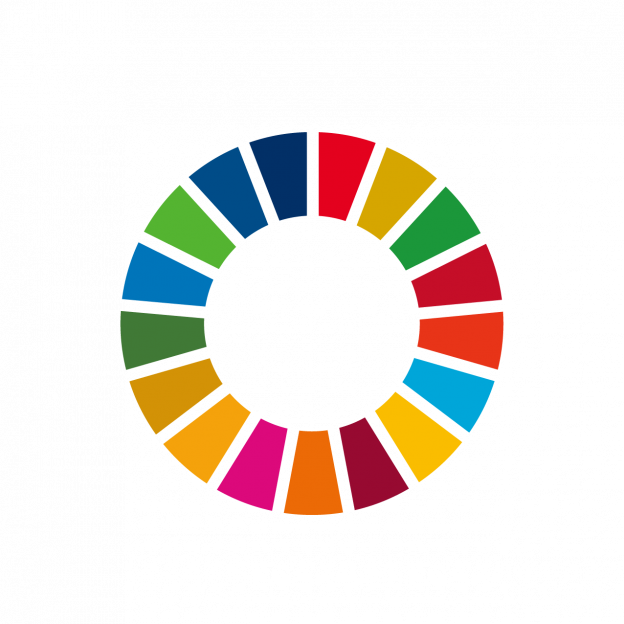
品川区立日野学園でプラスチック容器包装リサイクル推進協議会の出張授業をコーディネートしました
2025年1月16日、有限会社ラウンドテーブルコムのコーディネートで、SDGsの視点を入れた「わたしたちのくら…
-
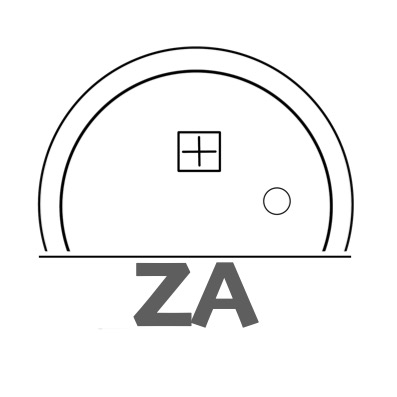
愛媛大学附属高校で開催「国際会議ESD Youth Summit 2024」でSDGs地域ポイントアプリを活用
—
by
in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, Rubric, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 愛媛愛媛大学附属高校で開催された「国際会議ESD Youth Summit 2024」で、有限会社ラウンドテーブル…
-
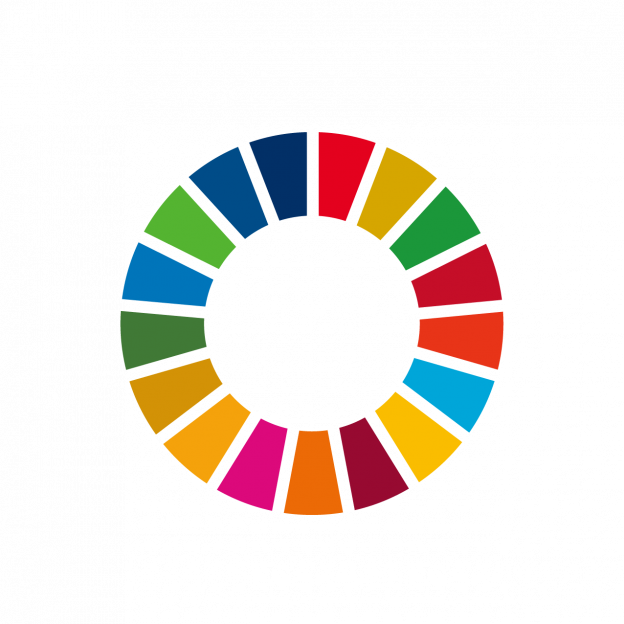
世田谷区立瀬田小学校でプラスチック容器包装リサイクル推進協議会の出張授業をコーディネートしました
2024年12月18日、有限会社ラウンドテーブルコムのコーディネートで、SDGsの視点を入れた「わたしたちのく…
-
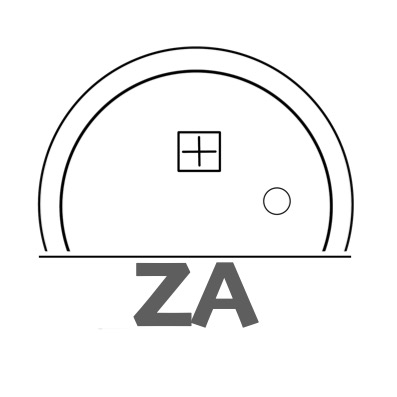
-
創業30周年を迎えて
1995年10月6日に創業して、30周年を迎える事が出来ました。 ここまで続けてこられたのも、一重に支えていた…
-

筑波大学附属坂戸高等学校の生徒たちとコラボ!
—
by
in ICT Concierge, ILPRC, K-12, News, PBL, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 坂戸本日、筑波大学附属坂戸高等学校のチーム「UNDIVIDED」の高校生2名とオンラインミーティングを行いました。…
-
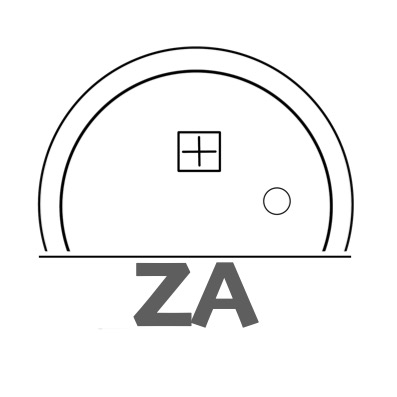
愛媛大学附属高校の高校生がSDGs地域ポイントアプリを活用
—
by
in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, Rubric, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 愛媛2024年度愛媛大学附属高校の生徒による探究学習プロジェクトで、有限会社ラウンドテーブルコムのSDGsアクティ…
-

-
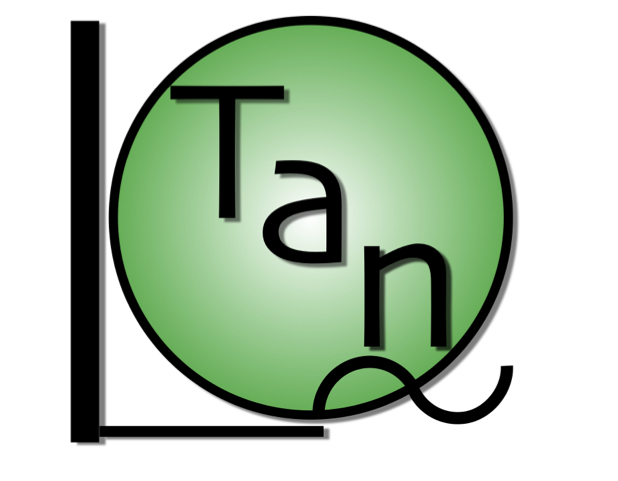
内閣府・地方創生SDGs官民連携プラットフォーム主催マッチングイベント「官民MEET東京」に出展
2024年7月12日(金)13:00~18:00、丸ビルホール(東京)で開催された、内閣府・地方創生SDGs官…