昨日のNHKの夜の番組で、日本にもすばらしい技術があるということで、宇宙の衛星の技術に日本の折り紙の技術が使われているという発言があった・・・
うーん、確かに紙を折るということからヒントを得た技術だと思うのだが、適切な表現だったかどうか・・・
東大名誉教授の三浦公亮先生のアイデアだと思う。
いわゆる「ミウラ折」。
http://www.miuraori.biz/
きっかけは、海外旅行をしている時に地図を大きく拡げていかにも観光客というような感じを出したくなかったという、三浦先生のとてもプライベートな動機があったというお話を以前聞いた。小さくたためて、しかも一気に大きく拡げることもできる技術。人工衛星の太陽電池もこの方式でたたんだり、拡げたりすることができる。
地図の場合、小さくたたんだ部分の隣の部分を見る事もとても簡単。そんな折り方なんですね。歩きながらその地域からはずれてもすぐに次の地域が確認できるなんて、すばらしい。
地図学会の方々と一緒に行ったJaxaツアーも面白かったし、衛星写真の地図のミウラ折バージョンなど、おもしろネタがたくさん。奈良遷都1300年祭でもこうした地図を取り上げると話題になるのではないだろうか?
ミウラ折は、飲料の缶の構造にも使われているとか。

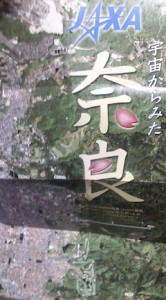
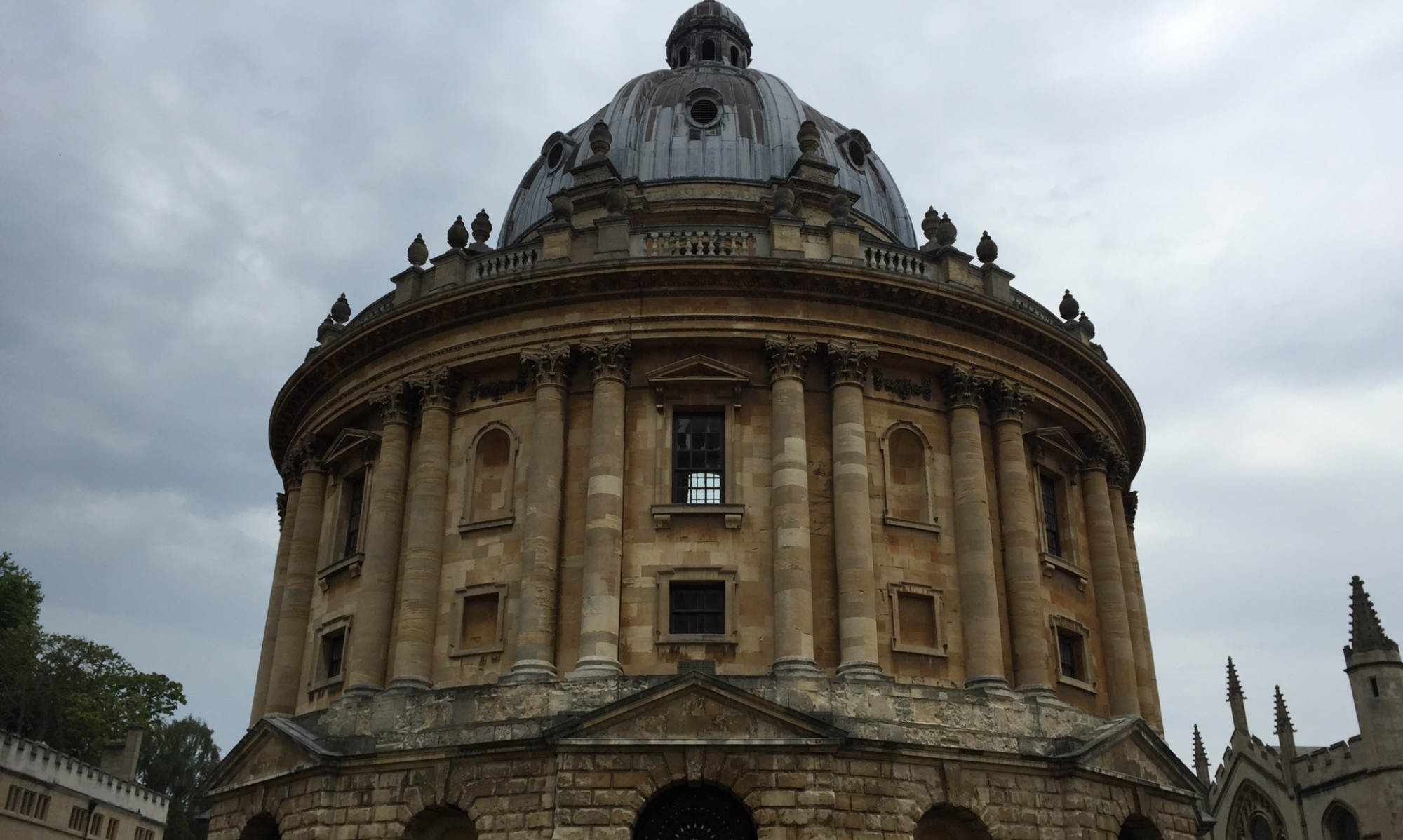
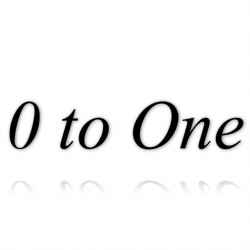


.png)