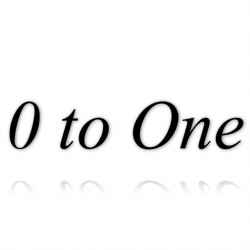「ClipCast」動画投稿サイト。ブラウザーだけで動画を編集できるサイトを目指している模様。ASPサービスで企業等にも提供していく予定もあるとか。どこまで編集機能がアップできるかが問題だろう。ログ管理機能についてはどうなっているのか、ぜひ知りたいところだ。
kuchi-CoMa
DAC(デジタルアドバタイジングコンソーシアム株式会社)が提供する、動画共有サイトを束ねた、口コミ動画広告宣伝サービス。つまり、広告動画をコンシューマーの協力により(CGM:Consumer Generated Media)、Web上を感染していくようなバイアルCMの手法で配布していくサービス。「Ask ビデオ」「フォト蔵」「FlipClip」「ワッチミー!TV」をネットワーク化したサービスを提供する模様。
ediPa
サン・マイクロシステムズ+MySQL
久しぶりにサン・マイクロシステムズの教育部門のメンバーと打合せをした。今回はある米国のソリューションをサンのマシンにのせて、教育機関に販売できないかというテーマでのブレインストーミング。会議の途中で、サンがMySQLを10億ドルで買収したことを知り、びっくり。最近オープンソースに傾倒してきたサンならでは決断だと思った。MySQL側もこれでレベルアップされたサポート体制を組む事ができ、いよいよミッションクリティカルな企業や政府部門でのLAMP(Linux, Apache,MySQL,PHP/Perl)の採用が期待できるのではないか。
弊社でもいち早くWorpress,Xoops,Moodle,Joomla,OpenPNE,NetCommons等のインストール及びサポートを教育機関などで活用していただいた実績がある。ますます、このあたりの利活用が進んで行くのではないかと期待している。
今回提案したソリューションもAJAX系だったので、話題としてはぴったりだったと思う。
学校連絡網システムを慶應義塾普通部に紹介
iKnow
 インターネットの世界で無料学習環境を提案している01 Virtual Schoolは、無料英語学習環境としてiKnow (http://www.iknow.co.jp/) を推奨することにしました。皆さんぜひチャレンジしてみてください。
インターネットの世界で無料学習環境を提案している01 Virtual Schoolは、無料英語学習環境としてiKnow (http://www.iknow.co.jp/) を推奨することにしました。皆さんぜひチャレンジしてみてください。
尚、この学習環境で学んだ時間なども、01 Virtual School: Diploma Cource での正式な学習時間としてもカウントいたします。
学校連絡網
学校の連絡網ってどうなっているのでしょう?
個人情報保護法ができて以来、「学校側が連絡網を作ってくれない」という話を耳にしたことがあります。だとしたら、運動会の朝雨が降っていたり、交通機関のストや事故で授業を遅らせたりなんて言う時にどうやって連絡しているのでしょう。
近所の小学生を持つお母さんの愚痴聞いていると、今の時代、親御さんがやる仕事が増えていることに気がつきました。学校が作ってくれない連絡網は自分たちで合意の上で作成しているようです。なんと最近では卒業アルバム等も自分達で作成しているとか。
何か寂しいお話です。
先日私の知人から紹介されたシステムがあります。学校・保護者連絡網をASPサービスで提供しているということです。なんと、これが安い!年間5万円程で学校全体の連絡網を個人情報を守りながら構築できてしまうということです。しかも、例えば修学旅行時に何らかの原因で旅程が変更になったりした時、現地から担当の先生が携帯電話で告知すれば、連絡網に参加している親御さんにすぐに連絡ができるようです。台風の影響で旅程を変更した時などが想定できますよね。今は携帯も国際的に使えるようになっていますからかなり便利かも。
「365日いつでもネット」(http://r365.jp/
)というサービスです。ご興味ある方はぜひ使ってみてください。このブログを見て登録したと記載してくれれサービスがあるようです。
私の運営するバーチャルスクール(01 Virtual School)でも採用してみようと思っている。
フレキシブルディスプレーの可能性
薄い紙のようなディスプレー、輝度を5倍から8倍に変えてくれるディスプレーとして紹介された、ヨーロッパ製のフレキシブルディスプレーを友人達に紹介している。
昨年六本木で開催された、東京国際映画祭でも採用され、この3月に開催される東京国際アニメフェアでも公式ディスプレーとして採用された。私自身もこのディスプレーを活用して、学生達のアニメ作品などをプレゼンテーションする機会を東京国際アニメフェアでは与えられている。現在作品を集めている最中だ。
昨年末の私の会社の忘年会でも実演をしてもらって、大好評。今回はその時に参加できなかった仲間も同行した。
私のアイデアとしては、やはり教育現場での活用。昨今文部科学省等も積極的に電子黒板という製品を学校現場に投入していっている。結構現場では好評だ。恐らく先生方の教え方を変更することなく、子供たちの前で黒板を使うような感覚で、プレゼンテーションができるからだろう。ただここで注意しなくてはならないのは、子供達からすると電子黒板では環境は圧倒的に変化してしまっているということだ。電子黒板を使うには遮蔽した教室が必要。暗闇の中での授業になる。ノートも取れない。暗闇が嫌いな生徒には圧倒的に不安感を与えてしまう学習環境になってしまう。しかも子供たちと先生の間に光源が必要で、電子黒板を指差す先生の手の影が映ってしまう。ある意味、特殊な学習環境になってしまうのだ。
それに対してこのフレキシブルディスプレーを活用すると、現在学校に入り込んだプロジェクターを活用しながら、バックプロジェクションの方法で映写すれば、輝度の明るい画面で、暗室にせずに、授業展開が可能になる。いっそうの事、こうしたソリューションを試作してみようということになった。
実験する場所はいくらでも想像できるので、 どんな物が出来上がってくるか、とても楽しみだ。

Zudeを杏林大学外国語学部に紹介
 2008年春から、「マルチメディア・イングリッシュ」の講義をお手伝いすることになった、杏林大学を訪問。外国語学部の倉林先生と面談を行った。今回はどのような授業展開をしていくのかを検討するブレインストーミングのような話し合いになる。マルチメディアという言葉自体、少し古い感じもしないでもないが、パソコンやインターネットを活用して、生きた英語を学ぶ機会を学生に創り出す授業ということだろう。
2008年春から、「マルチメディア・イングリッシュ」の講義をお手伝いすることになった、杏林大学を訪問。外国語学部の倉林先生と面談を行った。今回はどのような授業展開をしていくのかを検討するブレインストーミングのような話し合いになる。マルチメディアという言葉自体、少し古い感じもしないでもないが、パソコンやインターネットを活用して、生きた英語を学ぶ機会を学生に創り出す授業ということだろう。
この手の学習環境作りでは以前慶應義塾普通部に紹介したインターネットでの英語検定試験の導入(CASEC)、ビー・エヌ・エヌ新社からオファーのあったTOEIC向け実用英語学習問題集の2400問の問題作成プロジェクト(TOEIC TEST 500,600,700,800 速攻マスター、CD-ROM付き)などが思い出される。
今回は学生の学習ログを記録する為に、01 VIrtual Schoolでも活用している、01 Coaching Serverの活用や、01 SNSでも利用しているOpen PNEを使った SNSの活用、さらに学生の成果発表の場としてのZudeの利用など、様々な可能性を提案し、頭を柔らかくした状態で議論することができた。
担当する学生は、最大で60名程。TOEIC-IPの試験を課しているようで、その上位の学生を受け持たせていただけるらしい。この大学には後輩が3名、英語の選任教員として教えているので、彼らとの連携も見据えながら、楽しく有意義な授業が展開できればと願っている。
Zudeを関東学院大学工学部情報ネットメディア工学科でプレゼンテーション
 2008年春から、「メディアワークショップ」を講義することになった、関東学院を訪問した。関東学院大学は神奈川の八景島のそばにあるクリスチャン系の大学。工学部の海老根先生とは、以前営業で関東学院を訪問した時にお会いした。理事長にインターネット放送ソリューションを提案に行った時だ。。それ以降メールを何度か交換している間に、講義を受け持つ話になってしまった。以前お邪魔したときもそう感じたが、関東学院大学のファシリティはなかなかのもの。125周年記念事業も展開しているようで、今後のいっそうの発展を期待したい大学だ。ただ、こうした設備がある事が外部に十分に伝わっていない気がする。そうしたことも踏まえて、授業で一つのメディアを作って世界に関東学院の存在を知らしめられないかという狙いもあって、お引き受けした。
2008年春から、「メディアワークショップ」を講義することになった、関東学院を訪問した。関東学院大学は神奈川の八景島のそばにあるクリスチャン系の大学。工学部の海老根先生とは、以前営業で関東学院を訪問した時にお会いした。理事長にインターネット放送ソリューションを提案に行った時だ。。それ以降メールを何度か交換している間に、講義を受け持つ話になってしまった。以前お邪魔したときもそう感じたが、関東学院大学のファシリティはなかなかのもの。125周年記念事業も展開しているようで、今後のいっそうの発展を期待したい大学だ。ただ、こうした設備がある事が外部に十分に伝わっていない気がする。そうしたことも踏まえて、授業で一つのメディアを作って世界に関東学院の存在を知らしめられないかという狙いもあって、お引き受けした。
私が担当する学生は最大でも40名程だという。実際に使う事になるであろう教室や、講師控え室、教務の方々などにもひととおり挨拶することができた。あらかじめ考えておいたシラバスをご紹介したところ、快諾していただいた。大筋は合意できたと思う。学生にWebで公開できるコンテンツを制作してもらって、さらにその制作過程のコミュニケーションを記録、最終的はクラス全体での力でひとつの情報発信基地のようなインターネットメディアを創造していくという楽しい授業だ。
つまり、いままで私がやって来た活動の焼き直しとも言える。1997年から7年程続けた、慶應義塾普通部での「Webpageをつくろう」という総合学習的情報の授業、インターネットを通じて米国の高校を卒業してしまおうという、01 Virtual School の学習方法、多摩美術大学での「インターネット放送」の授業、既に5回目を迎えているK-12の生徒達の為のブロードバンド対応マルチメディアコンテストのBBCoach Project 、こうした活動の延長線上の授業が展開できる。
今回は新たな試みとしてMash Upという概念を取り入れた。Zudeというソリューションを活用して、学生達に公開ページを作らせることにした。恐らくこのソリューションを活用した授業としては日本で始めての授業、もしかすると授業で活用するのは世界で始めての試みになるかもしれない。米国ではMITのあるプロジェクトで活用されてはいる。
画像系、アニメーション系、動画系のソフトも充実した環境があり、さらに学内に放送局並みのスタジオまで揃っている大学の学生がどんなコンテンツを創ってくるのかが楽しみだ。