「鹿男あおによし」というテレビドラマを最近よく観ている。久しくドラマは観ていなかったのだが・・・何か惹かれるところがあるようだ。
背景に日本の神話があるからだろうか?それとも「のだめカンタービレ」のようなテンポがあるからなのだろうか?
いずれにしても「あおによし」という言葉にひっかかった。中学だか高校だか忘れてしまったが古典の学習で習ったような・・・調べてみると奈良にかかる枕詞。ここまでは学校での学習が役に立った。
しかし、びっくりしたのが、この後だ。インターネットで調べるといろいろ出てくるので面白い。「顔料の青丹(あおに)」+間投助詞 「よ」「し」との組み合わせだそうだ。しかし奈良に都が遷都される以前から使われているという事実から、きっと地域の産物からつけられた枕詞なのだろう。
学習コーチとして活動している01 Virtual schoolではこうした学習の方法は大歓迎だ!「あおによし」って何?と家族からゲーム感覚で質問されたとしよう。TVの話なら子どもも学習に入りやすいテーマだ。いざインターネットで調べてみるといろいろと出てくる。上記調べ方だとしたら、日本語または日本文化という学習目標を立てれば学習時間としてカウントできる。こんどは 「青丹」ってどんな成分だったんだろう?と調べて行けば、それは化学の学習としてカウントされる可能性があるわけだ。01 Virtual schoolではこうした学習を積み重ねて行く事で単位を修得していき、最終的は米国の高校の卒業資格を取得できるコースまで準備されている。無料で学習できる環境から、学習記録を残し、決められたルールに沿って単位を習得できれば、目標とする学習成果が求められる。そんな学習環境の充実を目指している。
よくよく考えてみると、社会に出てからもこうした学習の連続だ。こうした学習をそばで観ていてくれて、認めてくれる、そんな存在の学習コーチという職業を世間に広めて行きたいと願っている。
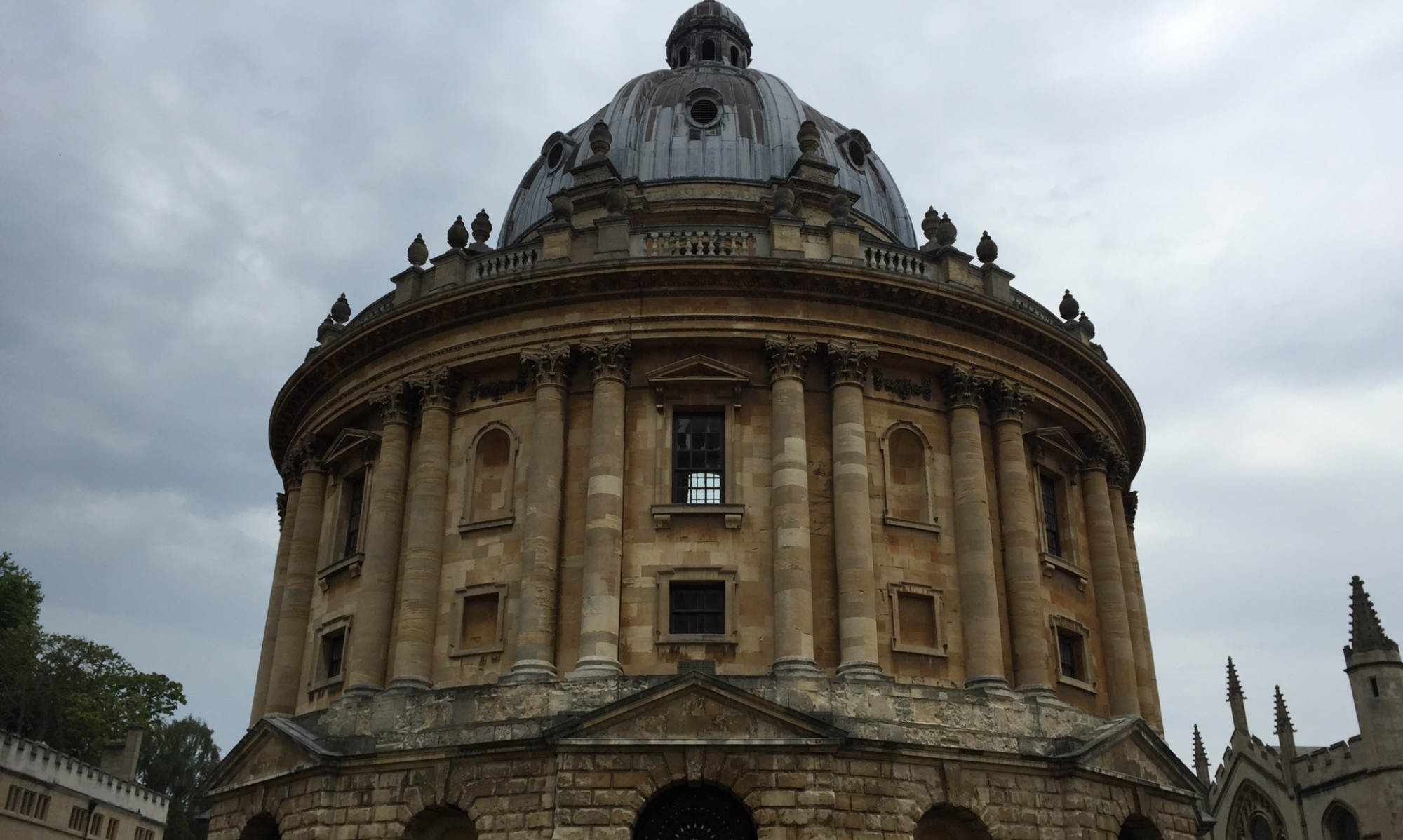
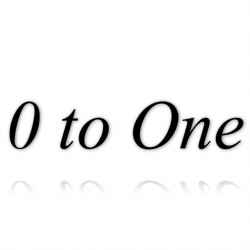

 インターネットの世界で無料学習環境を提案している01 Virtual Schoolは、無料英語学習環境として
インターネットの世界で無料学習環境を提案している01 Virtual Schoolは、無料英語学習環境として 第五回BBCoach Projectも参加者の応募が続々と送られて来ています。
第五回BBCoach Projectも参加者の応募が続々と送られて来ています。