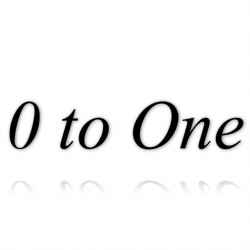慶應義塾大学の教養研究センターが主催する実験授業「アートと文学—ワークショップ Alfred Tennyson “The Lady of Shalott” の創造的解題:英語版創作をめざして」に参加してきた。
仕事の関係上これまでは参加できなかったが、今回が第三回目の開催。途中からの参加でも充分楽しめる内容だった。
今回は9月の連続授業の時にも関わっていたという、小関章ラファエル氏が講師。
4時半から6時半の2時間の予定の授業だった,参加者のディスカッションが白熱して30分程延長までしていただけた内容の濃いワークショップだった。
小関章ラファエル氏は劇団四季では『オペラ座の怪人』に関わり、その後、上智大学で神学を専門とされた方。『機動戦士ガンダム・ダブルオー / 機動戦士ガンダム00』『交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい』では神学考証に協力しているという。コンテンツの中の神学的アプローチ、ユング心理学を通してのアプローチというスタンスをもっているということ。この紹介だけでもぐぐっと引き寄せられてしまう、私にとっても興味津々の講師だった。
文部科学省 大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラムとしても活動の一環ということで、不破有理先生が担当されていた。不破先生と小関氏はアーサー王学会で知り合ったのだそうだ。なるほど、物語と神話というテーマになるとヨーロッパ文化に深く根ざしているアーサー王物語にもアプローチしておく必要ありということなのだろう。
9月の授業には確か高宮利行名誉教授も参加されていたと聞く。
”The Lady of Shalot”は、大学時代の同級生、葛生千夏さんのテーマでもあり、彼女の創作する素敵な音楽を聴いていた。授業でも接したし、英国旅行をすれば、ウォータハウスの有名な絵画に出会える。かなり読み込んだはずなのだが今回のワークショップではまた新たな発見も。
まずは読んでみようということになり、参加者の中から津森優子(翻訳家)さんが流暢なブリティッシュイングリッシュで朗読してくれた。1842年版のテキストと翻訳文の資料も配布されていたので、始めてこの詩に接した人にも内容が理解できる。実際この日始めてこの詩に接した参加者もいた。
その後小関章ラファエル氏のこのワークショップでのテーマが紹介された。「物語がわたしたちの伴侶となる」
「物語の構造を見る」というアプローチでこの詩を一緒に見てみよう、ディスカッションしてみようという試みだ。
松岡正剛「知の編集工学」等も紹介され、物語の構成要素を整理した後、ディスカッションの課題が出る。
「境界」というテーマでのディスカッションが出され、3〜4名程のグループに分かれて、一般的な物語の中での「境界」やこの詩の中での「境界」に関して自由ディスカッション。リーダーがその内容を発表という流れ。このあたりはKJ法等を活用して、カードを配布して、一人一人のアイデアをもっと引き出す為のブレーンストーミングの時間を取った方が良かったかもしれない。既に読み込んでいる人や経験を積んだ社会人等の意見が強く出過ぎたかもしれない。ディスカッションの内容は発表という形でしかデータとして残されてなかった。始めてこの詩に接した人のアイデア等ももう少し聞きたかった。恐らくこの活動だけでも授業としては成り立つだろう。
後半はJoseph Campbell のThe Hero with a Thousand FacesやThe Power of Mythなどの紹介もあり、映画Star Warsの映像等も交えたCampbellのインタビュー映像を英語で観て、気になった単語や文章を書き取りながら、ヒーロー物語の構造を各自が考えまとめる時間をもらう。さらにグループでのディスカッションを通して理解を深める。また、ダースベーダーがヘルメットを取るシーンがシャロット姫の決断と相通じる部分があるとい解説がある。グループ内では、男性と女性の探究(Quest)物語には少し構造が違う所もあるのではないかという意見もあり、またまた白熱。
このあたりは、Derek BrewerのSymbolic Storiesも紹介したくなった。
Symbolic Stories
そのインタビュー映像の中で、The Point of No Returnという言葉が出ていたのをきっかけに、シャロット姫の場合はどのスタンザがそれにあたるのかを議論したのも面白かった。シャロットの姫が若い恋人を観たシーン第8スタンザでは「I」という一人称の単語が始めて出てくるのだそうだ。シャロットの姫がラーンスロットを鏡で観た後に3歩いて、窓の外のキャメロットと睡蓮の咲くのを観て鏡が割れるシーンは第13スタンザ。シャロット姫がボートを見つけてそれに名前を書くシーンは第14スタンザ。いずれにしても「境界」を超えてしまった悲劇のヒロインの意思が表現された部分。さて、みなさんはどう考えますか?
物語の構成は3部構成が有効だという解説もあり。能なども序・破・急という展開があるそうだ。2部にはCentral Crisisが設けられて、3部で昇華させる、そこに人の心を動かす物語の成功方程式があるのではないかと。
来年度の関東学院大学で実施する私の講義「メディアワークショップ」でも影響を与えてくれるアイデアが満載されたワークショップだった。
授業後の交流会では、ヨーロッパ神話の起源や、カオスから生まれてくる神話、日本の神話との繋がり、古事記、能、翁舞、プロジェクトマネジメント等の話題でさらに盛り上がった。