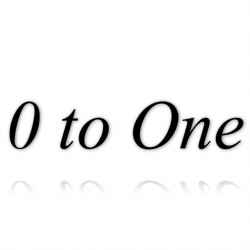主催: 国土交通省
場所: 東京都千代田区内神田1-11-11 藤井第一ビル4F
日時: 3月8日(日) 10:00~17:30
参加費: 無料
「地球地図」普及イベント
地球地図を使って授業運営してみませんか?
教員の方々に朗報です!
「地球地図」ワークショップの開催ご案内
「地球地図ワークショップ」運営事務局
1992年、ブラジルで開催された「地球サミット」の際、日本の国土交通省(当時の建設省)が、環境問題を解決するための地理情報の整備を呼びかけたことから「地球地図」プロジェクトが始まりました。
「地球地図」は、誰もが無料でホームページからダウンロードできるデジタル地図です。世界各国の公的な地図作成機関が作成し、それを持ち寄ることで整備しており、日本の国土地理院がプロジェクトの推進組織であるISCGM(世界地球地図整備委員会)のとりまとめ役をしています。
「地球地図」は、「標高」「土地被覆」「土地利用」「植生」「境界」「水系」「交通網」「人口集中域」の8つの階層の地理情報を持っており、それらを重ねて表示をしたり、その上に様々なデータを重ねることができます。世界統一仕様で作成されていますので、世界各地の地図データを同じ条件で作成したり、比較することができ、海外のNPOや学校、研究者等との情報交換・共有の際にもご活用いただけます。
この度、昨年11月の全球陸域をカバーする「地球地図」第1版完成を機に、環境、防災、教育等様々な分野で活動されている方々を対象に、「地球地図ワークショップ」(「地球地図」を使ったデータ作成の講習会と意見交換会)を下記のとおり開催いたします。より多くの方に「地球地図」を活用していただきたく、ここにご案内申し上げます。
記
主催: 国土交通省
場所: 東京都千代田区内神田1-11-11 藤井第一ビル4F
JR神田駅(西口) 西口商店街を抜けて 徒歩5分
日時: 3月8日(日) 10:00~17:30
参加費: 無料
プログラム
【午前】10:00~12:00
1)「地球地図プロジェクト」の概要説明(国土交通省)
2)「地球地図」のデモ等 (国土地理院)
3)「地球地図」の活用事例の発表
~環境問題、防災、教育などにおける「地球地図」の様々な活用事例(仮題)
【午後】13:00~17:30
ワークショップ
4)事務局の準備したデータを使って「地球地図」の利用方法を学ぶ。
5)参加グループに分かれオリジナル地図を作成。
6)「地球地図」の活用についての意見交換。
〔備考〕
※ 5)の成果は後日提出いただき、ご承諾をいただいた作品については地球地図の活用事例としてホームページ等で公表させていただきます。
※ ワークショップの際には、研究・調査や活動で作成されたデータを持参下さい。
例)画像・動画・テキスト(地図の上に貼りこむことができます)
例)統計データ(地図の上にグラフをつくることができます)
例)緯度・経度の位置情報を含むエクセルデータ(自動的に地図上に読み込むことができます)
他にもいろいろなデータを使用できます。詳細は事前に下記事務局にお問い合わせください。
○事務局:「地球地図ワークショップ」運営事務局(みんなの「地球地図」プロジェクト内)
info@globalmap.org このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にして下さい
○みんなの「地球地図」プロジェクトホームページ
http://www.globalmap.org/
お問い合わせ先: gis@roundtable.co.jp
Worldmapper
イギリスのシェフィールド大学、アメリカのミシガン大学が協力して、様々な統計データを地図上にマッピング。面積比で世界の様子を再構築している。
このデータは15才から24才の年齢層での識字率を表している。なんと日本が一番だ!教育立国日本が浮かびあがった。アジアも頑張っている。
明治維新前のデータがぜひ見てみたい。
「みんなの地球地図プロジェクト」の活動にも影響が出てくる可能性を感じた。
地球地図と環境問題
「地球環境SOS!地球地図が地球を救う」というシンポジウムに参加してきた。
シンポジウムの詳細はこちら
NPOや学校での地球地図を使った実践事例の紹介や、専門家集団による学術的活用(絶滅危惧種の動物の生態データや、渡り鳥の生態調査データ等)の事例まで、幅広く地球地図の活用を世の中に知ってもらおうという、国土交通省のイベントだ。
ここで問題だと思ったのが、山根一眞、眞鍋かをりといった著名人達をいきなり引っ張り込んで、パネルディスカッションに参加させていたこと。恐らく一般大衆の方に広く知ってもらう為という名目で、どこかの広告代理店あたりから出て来たアイデアかと思うのだが、企画倒れだったのではないか?どうも話のポイントがずれているのだ。地球地図を理解しないまま、ディスカッションを進めようとするから、 ちんぷんかんぷんのパネルディスカッションになる。一夜漬けの知識で地球地図を語ろうとしているのがみえみえ。一番のポイントはその縮尺の解釈だ。
地球地図は恐らく国防上の理由もあるだろうが、Google Map等に比べるとその扱う大きさが違う。あまり細かい地域データまでは扱えない。もっと地球規模的なデータを扱うのに特性があるところを見過ごしてしまうと、議論が噛み合なくなる。忙しいこともあるかもしれないが、特にパネルディスカッションをリードする役目を負った仕事を引き受けたのなら、そのあたりのポイントだけはおさえておいて欲しかった。または周囲のアレンジャーがきちんとポイントを説明しておくべきだっただろう。
いずれにしても日本が言い出しっぺの地球地図、ようやく世界的規模のデータがそろいつつあるので、うまく普及して欲しい。
 今後も01 Virtual Public Schoolの活動も通じて、応援していきたいと願っている。
今後も01 Virtual Public Schoolの活動も通じて、応援していきたいと願っている。
地球地図の学校2-5
国土交通省「地球地図の学校」プロジェクト第二弾
タイの生徒のプレゼンテーション
地球地図の学校2-4
国土交通省「地球地図の学校」プロジェクト第二弾
タイの生徒の日本の生徒の交流
地球地図の学校2-3
国土交通省の「地球地図の学校」プロジェクト第二弾
日本の中学生による英語のプレゼンテーション。
地球地図の学校2-2
国土交通省の「地球地図の学校」プロジェクト第二弾
慶應義塾普通部太田先生による交流国タイの紹介。
地球地図の学校2-1
国土交通省の「地球地図の学校」プロジェクト第二弾
慶應義塾普通部太田先生による導入編。
地球地図の学校1-3
地球地図の学校
慶應義塾普通部
太田弘教諭