原宿のアメーバスタジオ で、保阪尚希さんの番組に出演してきました。
「インターネット放送局」での生番組、初出演です。
多摩美術大学で「インターネット放送」をテーマに講義を持った経験がありますが、自分がその番組の出演者になるとは夢にも思っていませんでしたが。
保阪さんも教育問題にはとても興味があるようで、私を呼んでいただいてようです。
インターネットを活用して学習する人たちをサポートする学習環境を作りづけて来ていることをお話し、また実際の学校現場の実績も重ねて来たことをお話できました。途中、一人一人の情報をきちんと整理して学習コーチングするには、ブログやチャットを利用するなんてお話もしました。私が、保阪さんのブログ「保阪流 」をきちんと読んでいたので「ハワイにいても学習コーチはできるんですよ」と発言したら(保阪さんは1月にハワイに行っていたようです)、頭の良い人で、台本を一気に飛ばして別のコーナーのハワイの話題に進んでいました。その後の周囲の人たちがどうやって、話題を戻すか少し心配になる場面でもありましたが。でも出演者みんなが協力しあって生番組をを創り込んで行くという醍醐味を味わえたと思います。少し緊張したけど、とても楽しい体験でした。
 現在01 Virtual SchoolではIEN(International Exchange Network)さんの海外バーチャル留学サポート(高校部門)も応援しています。海外留学をするという決断をするというその第一歩を評価すべきだという保阪さんの発言も納得。私の持論でもある「0 to 1」「ゼロから一歩踏み出す勇気を評価してあげたい」 という発言もすることができました。
現在01 Virtual SchoolではIEN(International Exchange Network)さんの海外バーチャル留学サポート(高校部門)も応援しています。海外留学をするという決断をするというその第一歩を評価すべきだという保阪さんの発言も納得。私の持論でもある「0 to 1」「ゼロから一歩踏み出す勇気を評価してあげたい」 という発言もすることができました。
また、「悩メール」というコーナーでは、アレルギーの人の話題になり、皮膚アレルギーを保阪さんも経験した話もあったので、私のこれまでの経験からバーチャススクールにもアレルギー経験者が25%もいるなんていうデータもお話することができました。少しでもみなさんのお役に立てる学習環境創り込めたらと願っています。最終的は私の夢は無料で学習できる環境を整備していくことでしょうか。 プロジェクトはいつまでも続いて行きそうです。
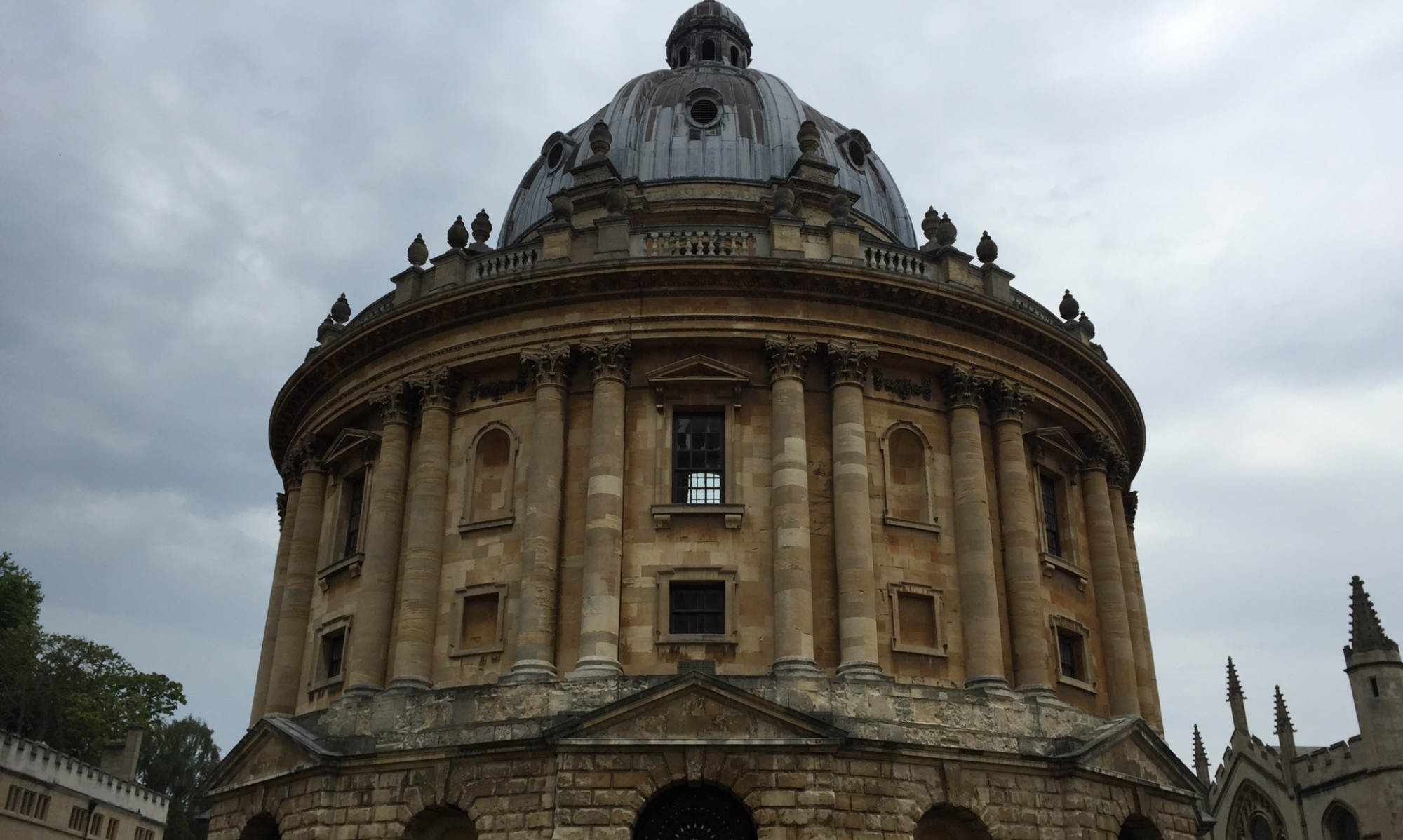
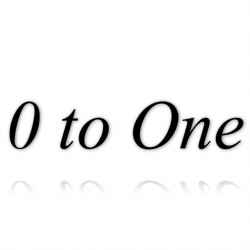

 インターネットの世界で無料学習環境を提案している01 Virtual Schoolは、無料英語学習環境として
インターネットの世界で無料学習環境を提案している01 Virtual Schoolは、無料英語学習環境として 第五回BBCoach Projectも参加者の応募が続々と送られて来ています。
第五回BBCoach Projectも参加者の応募が続々と送られて来ています。
 2008年春から、「マルチメディア・イングリッシュ」の講義をお手伝いすることになった、杏林大学を訪問。外国語学部の倉林先生と面談を行った。今回はどのような授業展開をしていくのかを検討するブレインストーミングのような話し合いになる。マルチメディアという言葉自体、少し古い感じもしないでもないが、パソコンやインターネットを活用して、生きた英語を学ぶ機会を学生に創り出す授業ということだろう。
2008年春から、「マルチメディア・イングリッシュ」の講義をお手伝いすることになった、杏林大学を訪問。外国語学部の倉林先生と面談を行った。今回はどのような授業展開をしていくのかを検討するブレインストーミングのような話し合いになる。マルチメディアという言葉自体、少し古い感じもしないでもないが、パソコンやインターネットを活用して、生きた英語を学ぶ機会を学生に創り出す授業ということだろう。