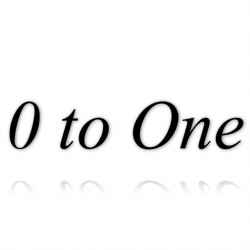インタラクティブ(対話型)・アシスタントというソリューションをご存知だろうか?
データベースの構築から必要になるのでかなり高額なシステムになるが、その効果が出てくる企業もある。
NTT東日本のホームページを見て欲しい。
http://www.ntt-east.co.jp/
トップページの左上「お客様サポート」の欄をクリックして、次のページの「質問する」をクリックすると、Pop Up Windowが開く。「ご質問をどうぞ」というWinodowの中に、キャラクターが登場して、質問のフォームが出てくる。このキャラクターはFlash のアニメーションで作成されていて、なかなか表情が良い。瞬きもリアルで親しみのあるキャラクターだ。
面白いのがこの質問フォームが自由文を受け付けてくれる事。「引っ越しをしたいのですが、手続きは何をしたら良いですか?」というような文章を入力しても的確な反応がある。
これはデータベースの作り込みをしているからだ。一般的に検索エンジンは、人間が介在して登録していく方法と、ロボットが情報を収集していく方法の 2種類 に分けられるだろう。後者の代表的なサービスがGoogleだ。膨大なWebの世界の情報を整理するにはロボット検索によって、データベースを構築してい く手法が一般的になりつつある。以前はYahooは人間がデータベース構築をしていたが、現在ではロボット型との組み合わせになってきている。
一方で企業のホームページも膨大な情報量になりつつある。最近では無料のロボット検索エンジンが配布されていたり、Googleの検索エンジンを活用して自社内のWebの検索を実施している企業も少なくない。
しかし、この状態で問題が発生してきている。例えばNTT東日本はgooのロボット検索エンジンを自社で開発してきたがが、最近ではそのデータの量 が膨大 すぎて、消費者の質問に対して的確なページを表示させることが難しくなってきたようだ。「引っ越し」という言葉で検索しても、一番消費者に見せたいページ を検索のトップに表示させることが難しくなってきた訳だ。そこであえて見せたい検索結果をページの一番上に引っ張ってくるという仕組みを考えることになっ た。
もちろん検索という行為に慣れているネチズンであれば、このソリューションで充分なのかもしれないが、あまりにも無味乾燥なサービスになる。そこで 登場し てきたのがインタラクティブ・アシスタントだ。キャラクターには表情がある。実は感情もセットアップしておくことも可能だ。例えば,意地悪な言葉を質問し 続けると、5分間は退席してしまって戻ってこないというプログラムを埋め込むことも可能だ。これなら子どもも喜んで検索してくれるだろう。高齢者の方も質 問にチャレンジしてみようという気持ちになるかもしれない。
このNTT東日本のサイトでもこんな遊び方ができる。
「あなたの名前は?」→「鈴木ひとみ」であるという回答がある。
「私の名前は山田太郎です。」→「山田太郎さんですね。」
「私の名前は何ですか?」→「確か、山田さんですね。」
とあたかも対話をしているかのように振る舞ってくれる。
なんとも、ほんわかムードの中で質問することができるのだ。
さて、こうしたシステムの効果をどう考えるか。
お客様サポートで最もコストがかかるのが、電話応対やメールでの対応である。それは必ず人手を介して時間をかけなければサービスに繋がらないからだ。必ず 人件費がかかる。単純な質問になればなるほどこの人件費はばかにならないものになる。毎日毎日同じ質問を答える為にコールセンターを用意して、人を配置し ておかなければならないからだ。
この単純な質問を以下に減らすかが、コスト削減の最も効果的な施策になる。
また、一方で売上増が見込めるキャラクタービジネスへの発展も考えられる。そのうち「インタラクティブ・アシスタント・ビユーティーコンテスト」な んてい うのができるかもしれない。また既にキャラクターを持っている企業は、そのキャラクターに直接消費者にサービスを提供させることが可能になる。
つまり、この仕組みはコスト削減と売上増が見込まれるソリューションなのだ。このあたりをうまく考える経営者層にこの仕組みを提案していきたいと思い、現在このソリューション販売のコンサルティングを開始した。